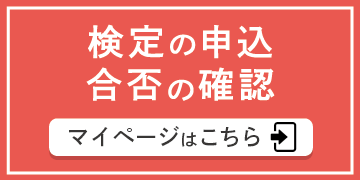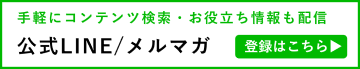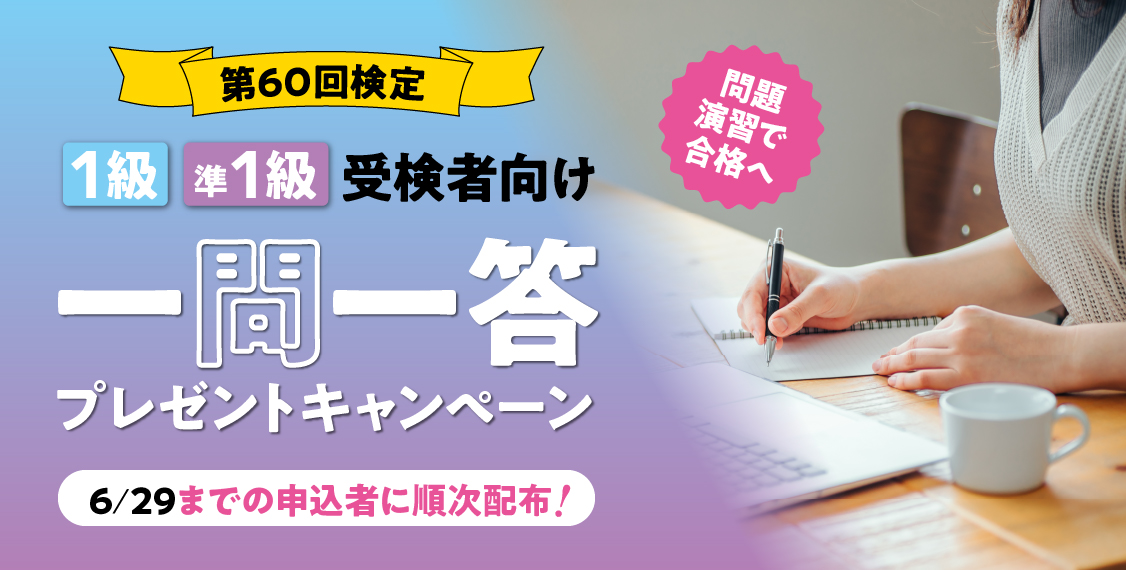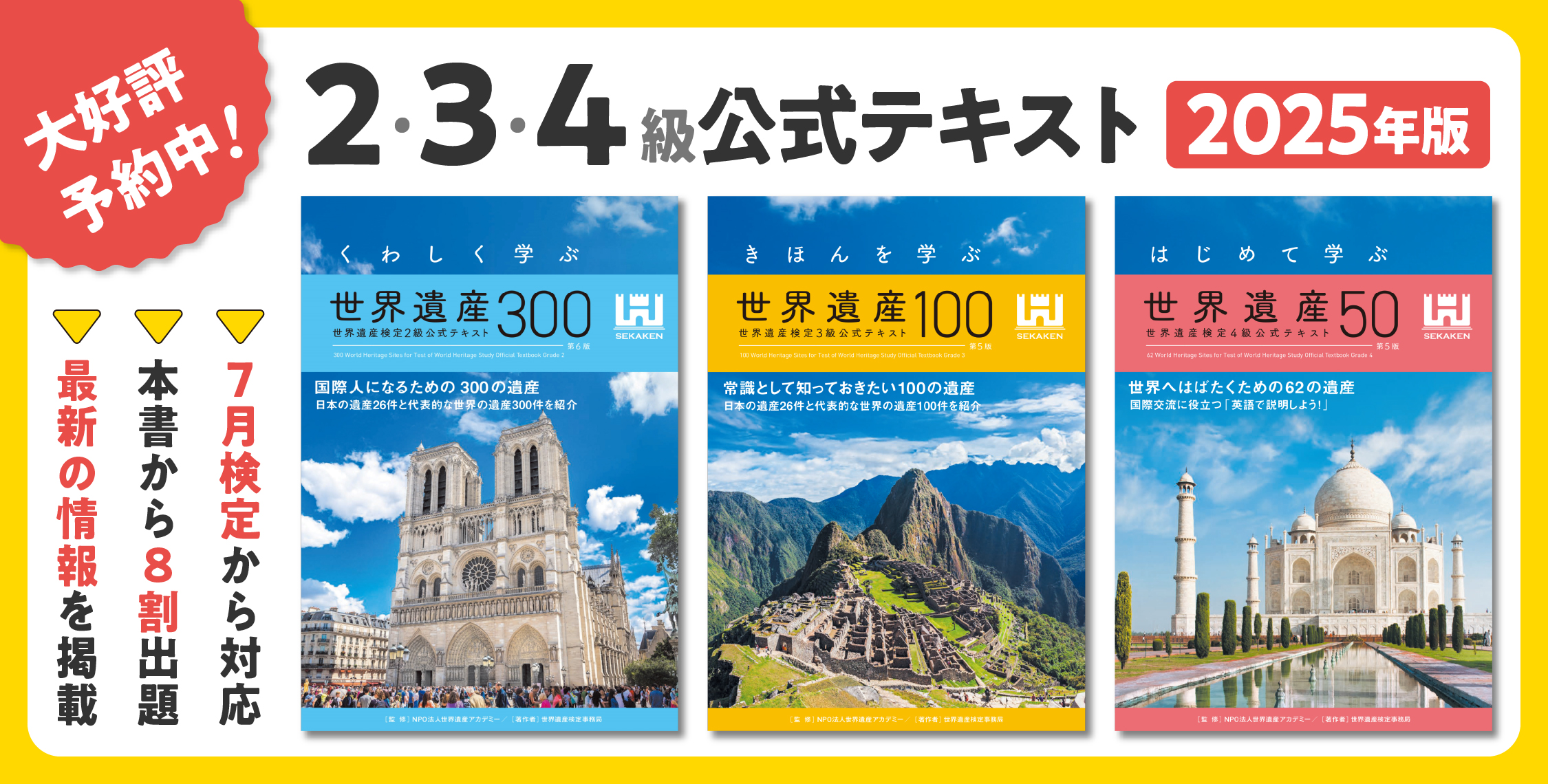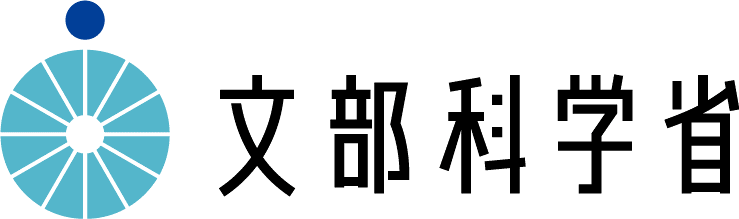認定級 マイスター
尾之上 剣成さん
法政大学文学部
―― まずは世界遺産検定をご存知になったきっかけを教えてください。
高校生のころまでは世界遺産というものをそもそもあまり知らなかったのですが、自分が共通テストを受けた年の現代文の問題にル・コルビュジェが出てきて、家に帰ってから母親に話したんです。そしたら母親はそれが世界遺産であることを知ってて。自分は負けず嫌いなところがあるので、「何で母親が知っているのに自分は知らないんだ」という気持ちになりました。
それで世界遺産について調べ始めて、ある日、本屋に行ったら世界遺産検定のテキストを見つけて、こんなものがあるんだと思って。ちょうど春休みで時間もあり、地理学科に入学することも決まっていて、地理と世界遺産は関係しているところも多いので、これをきっかけにちょっと勉強してみようかなと思い、2級のテキストを買いました。

出身が静岡県なので富士山を毎日見ていて、富士山が世界遺産だということは知っていたのですが、それ以上のことは本当に知らない状態で。そこから世界遺産検定に出会って勉強し始めたという感じです。
―― そこから1級、マイスターとステップアップしていった経緯を教えてください。
大学1年の夏に2級に合格して、すぐに1級のテキストも購入しました。ただ、なかなか勉強する時間が取れずにその年の12月の受検はしなかったのですが、2年生の5月頃に大学からメールで世界遺産検定の案内が来て、割引で受けられるということだったので、せっかくだしやってみようと。試験まであまり時間がなかったのでそこからは一気に猛勉強しましたね。1級と2級では全然分量も違いますし、大学の授業も忙しいし、地獄の日々みたいな…(笑)。まあでも楽しかったので勉強は続けられました。
結果として一回で合格できたので、「じゃあもうこの勢いでマイスターまで行っちゃうか!」という気持ちになりました。その年(2024年)は「佐渡島の金山」が新たに登録されたり、パリオリンピックが開催されたりして、世界遺産関連の報道が結構多かったですよね。だから出題内容も佐渡島かパリかどちらかが出るような予感がしたので、もうこの年に一気にやってしまおうという感じで、その2つを中心に勉強して挑みました。
―― そのスピード感で、マイスター最高得点までたどり着いたのはすごいですね。世界遺産アカデミー賞を受賞された率直な感想をお聞かせください。
うれしい気持ちがあるのと同時に、驚きが勝っています。結構いい点数が取れただろうという自信はあったのですが、検定事務局からメールが来て、もしやと思って見たら、まさかの受賞連絡でした。本当に驚きました。急いで母親や父親、祖母にも連絡しました。世界遺産検定はテレビでも取り上げられることが多いので、友達からは「テレビ出られるじゃん!」みたいなことも言われて(笑)。テレビではないですが今回インタビューを受けることになり、何となく道が開けたような実感を持っていますね。
(※編集注)世界遺産アカデミー賞は第60回検定から選考基準が変更となりました。詳細はこちら
―― 試験に向けてはどのような勉強をされたのですか。
自分はうまくまとめるのがあまり得意じゃないので、1級に関してはひたすら暗記ですね。もう本当にずっとテキストを持ち歩いていて、大学の休み時間にも、電車のなかでも、家で寝る前にも読んで、とにかく覚えるという。正直、1級が一番しんどかったですね。最後の最後、試験直前などはある程度勉強するポイントを絞りました。比較的新しい遺産や、オリンピックがあったのでフランスに関係する遺産、最近話題になっている産業遺産などのほかに自然遺産も加えて、登録数が少ない分野を中心に勉強しました。

マイスターについては上巻を持ち歩いて、用語のところをひたすら読んでノートにも書き出し、重要語句を抽出して、それを使って自分で文章を組み立てられるようにするという練習はしていました。過去に何度も出題されている語句を中心に、色々なパターンで文章を書けるように準備しました。
―― 学んでいくなかで、特に印象的だった遺産があれば教えてください。
まずは「アントニ・ガウディの作品群」ですね。自分はスペイン語を第二外国語で勉強していて、スペインの文化に興味があり、去年の9月頃に初めての一人旅で実際に行ってきたんです。サグラダ・ファミリアの「生誕のファサード」に登ってバルセロナの街並みを眺めたり、礼拝堂でミサを見たり…。20年間で一番感動したと言っても過言ではないです。ステンドグラスや彫刻の美しさに本当に心動かされました。勉強したうえで訪れると、彫刻一つにしてもそこに込められた意味や物語の奥深さを感じられるので、ある程度の知識を持っているのとそうでないのとでは全然違うと思いますね。
家族と一緒に韓国にも行ったことがあり、宗廟なども見学しましたが、当時はまだ2級だったので、今の知識を持って改めて行ってみたいなとも思います。

バルセロナではガウディの作品群はほとんど見て回り、カタルーニャ音楽堂にも行って、そのあとマドリードやトレドも訪れました。歴史地区を歩いているとタイムスリップしたような感覚になり、自分がいま世界遺産にいるんだという実感がしてすごくうれしかったですね。

これから行ってみたい世界遺産や国も色々ありますが、特に行きたいのはドイツの「ケルンの大聖堂」です。2級のテキストで初めて見たときに、夕焼けのなかそびえる大聖堂の姿がすごくきれいで印象に残っていて。光と高さでキリスト教の世界観を表現するというゴシック様式の特徴もそこで知りました。
―― 世界遺産を学んだことで、ご自身の生活のなかに活きている部分はありますか。
実は先月までフィリピンに1カ月ほど留学に行ってきました。もっと世界の色々なところを旅したいと思っていますが、それにはある程度言語ができたほうがいいじゃないですか。自分は外国の方と話すのもあまり得意ではなかったので、外国の友達を作り、少し自信をつける意味でもよいかなと思ったんです。
その留学でも、世界遺産の知識が現地の方とコミュニケーションを取るうえで活きたと思います。フィリピン人の先生と話すときに「コルディリェーラの棚田群」が見てみたいんです、という話をしたり。世界遺産というのは、その国の人にとってはアイデンティティになっていることも多いと思うので、それを知っていて会話にできるのは、他国の方とのコミュニケーションの助けになることを実感しました。
大学でも地理学科にいて世界遺産が絡む部分もあるので、予備知識を持ったうえで授業に臨めたり、レポートを書くときに世界遺産を中心に構成する、といったことができています。3年生からはゼミが始まりますが、旅行系のゼミに所属することが決まりました。旅行好きが集まるので、メンバー同士経験を共有し合えたらなと思います。
―― 将来の進路希望について、差し支えない範囲で教えてください。また世界遺産の知識を今後どのように活かしていきたいですか。
最近は国際線の客室乗務員として働きたいと考えています。空港には結構憧れがあって、色々なスタッフさんが働かれていると思うのですが、皆さん英語をはじめとして色々な言語がしゃべれたり、さまざまな国に行かれる人がいたり。そこで世界遺産の知識を活かせる場面もあるのではないかという気がしています。
教師として教えたいという想いもあるので、大学では教職の課程を取っていて、高校の地理歴史や公民、中学校の社会の免許を取りたいと思っています。歳を重ねて機会があれば、子供たちに地理や世界遺産を教えたいと考えています。
世界遺産条約のなかでも教育広報活動が必要であるということが述べられていますが、自分も今後、世界遺産教育や広報活動、あるいは世界遺産の保護に携われたらよいなと思っています。地元の富士山もやっぱり今、観光問題などを抱えているので、そういった課題解決に関わったり、PR活動ができたらいいですね。

より多くの人に、世界遺産がどんなもので、守らなければならないものなんだということを伝えていけたらと考えています。
(2025年4月)