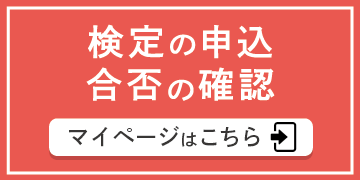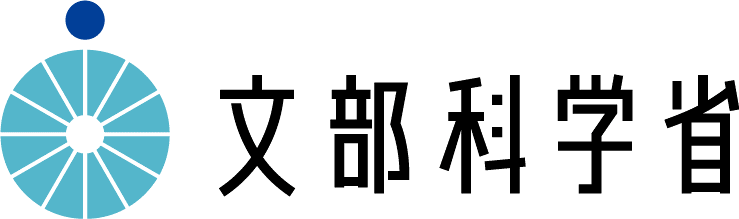初めてフランスを訪れた時、空港でフランス語は通じないし市内へのバス乗り場にバスは来ないし、もうぐったりした状態で空が暗くなったパリに到着しました。でも若かったのでしょうね、荷物だけホテルに置くと、セーヌ川の見える橋まで散歩をしました。その時に見た、夜空に浮かぶノートル・ダム大聖堂が本当に美しかったことを覚えています。フランスに来たんだなと実感した瞬間でした。
2019年4月15日に起こった火災でノートル・ダム大聖堂の屋根から炎と煙が上がる姿は、胸が痛くなるものでした。パリで暮らす人々やフランス人が感じた痛みはその比ではなかったでしょう。
パリのノートル・ダム大聖堂は歴史的建造物とはいえ、フランス国内で100以上もある教会や聖堂のうちのひとつに過ぎません。しかし、そのひとつの聖堂の火災で、これほど多くのフランス国民が言葉を失うほどに傷つき、大統領が悲痛な面持ちで国民にメッセージを発するのには理由があります。
1つ目が、パリの中心にある、という点です。パリの発祥の地がノートル・ダム大聖堂の立つセーヌ川のシテ島です。パリの区割りはシテ島を基点として、渦巻きのように1区から20区まで定められています。厳密には、シテ島は真ん中で1区と4区に分かれていて、ノートル・ダム大聖堂は4区に含まれるのですが、パリの中心となる島に立つシンボルのような存在です。
次に、ノートル・ダム大聖堂は、パリの人々が日ごろからよく目にしているものだったという点です。パリ市は東京などと違って小さいだけでなく、あまり起伏がなく平らな都市です。モンマルトルの丘から眺めるとそれがよくわかります。それに加え、パリでは景観保護に力を入れているため、ノートル・ダム大聖堂やアンヴァリッド、エッフェル塔などは、建物自体の見た目を邪魔するものがなく、モデルのようにすっと立っています。これこそ、パリが世界遺産に登録されている価値です。特にノートル・ダム大聖堂は、セーヌ川沿いという開けた場所に建っていることもあり、多くの人々が日常生活の中で目にする見慣れた風景でした。
そして一番重要なのが、フランスが「カトリックの長女」を自負する国家だという点です。実際には、洗礼を受けたカトリック信者が国民の大多数を占めるわけでもないですし、毎週日曜には教会の礼拝に通うという国民も多くはありません。プロテスタントが多いアメリカなどにいる時の方が、よっぽどキリスト教の国にいる気がします。
しかし、それでもフランスの国民の多くは、自分はキリスト教だという思いを持っています。歴史的にそれだけキリスト教が社会や生活の中に浸透していることもありますし、イスラム教世界などとの対比からそう考えているという側面もあると思います。
歴史的に見ると、ゲルマン民族のクローヴィスが、現在のフランスやドイツ、イタリアの元となるフランク王国を建国した時に、妻の勧めでカトリックに改宗したことが始まりです。当時は国王がカトリックに改宗したということは、国民の全てがカトリックになったことを意味しました。その後も、カトリックの国家を標榜するオーストリアのハプスブルク家と競うようにして、フランスはカトリックの守護者の役割を演じてきました。
フランス王国とカトリック教会の関係が常に良好だったわけではありませんが、政教分離のフランス共和国にあっても「フランスといえばカトリック」というほどに、密度の濃い関係が作られてきました。ノートル・ダム大聖堂は、そうしたフランス国民の心理を具体的に表す建物だと言えるのです。だから、同じくパリのシンボルであるエッフェル塔が倒壊するよりも、恐らくショックは大きいのだと思います。
(2019.04.19)
<つづく>