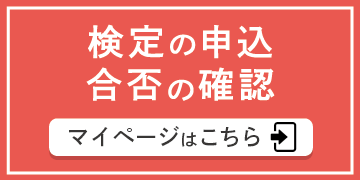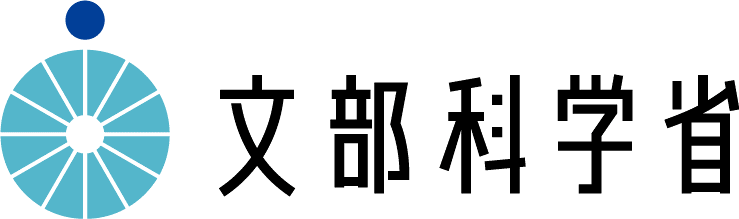今年もあっという間に一年が終わろうとしています。本来であれば、今頃はオリンピックの余韻に浸っているはずだったのですが、今年は新型コロナウイルスに終始した一年でしたね。しかし、オリンピックの代わりに良い面で話題になったのが『鬼滅の刃』でした。今年の夏過ぎまでは、タイトルの読み方もわからなかった僕ですが、先日、職場の同僚に借りて全巻読んでみました。
ストーリーは、ものすごく簡単に言うと、鬼になってしまった妹を人間に戻すために兄が奮闘し、その兄を含む人間たちが力を合わせて鬼を生み出す大親分のような鬼を倒すというものです。ざっくりし過ぎていて怒られちゃいそうですが。
基本的には鬼と人間しか出てこないのですが、物語全体を通して、鬼が圧倒的に強いんです。人間なんてほんと簡単にバタバタと殺されてしまう。それが1,000年以上も続いています。そこで人間たちは「鬼殺隊」という剣士の集団を作って、何百年もの間、鬼退治を続けてきました。では、個として圧倒的に強い「鬼」と、個としては弱く殺され続ける「人間」と、どちらが「強い」のでしょうか。
世界遺産に登録されている自然には、『知床』のヒグマや、『シュンドルボン』のベンガルトラ、『カンペチェ州カラクムルの古代マヤ都市と保護熱帯雨林群』のジャガーなど、さまざまな「強者」と呼ぶべき生き物が生息しています。しかし、それらのほとんどは絶滅の恐れがある生き物です。それに引き換え、彼らと1対1で対面したらまず敵わない「弱者」とも呼べるナマケモノやシマウマ、アイベックスなどは、絶滅の危機には直面していません。もちろん、人間だってそうです。
実際の自然界では、強いからといって確実に獲物をしとめられるわけでもないですし、弱いからといって必ず喰われてしまうということもありません。「適者生存」で、環境に適した生存戦略をさまざまな生き物が採りながら「種」として残っています。つまり「個」の強さなんてほとんど意味がない。「個」としてどちらが「強い」なんて設問自体がナンセンスなのです。『鬼滅の刃』で考えると、「個」がどれだけ殺されたとしても、「種」として鬼に立ち向かった人間が次の世代に遺伝子を受け継いでいったわけです。
「種」として環境に適応していく上で重要なのが多様性です。自然や環境には、もう無限ともいえる状況があります。その無限に広がる環境に適応するために何が最適なのか、はっきり言ってわかりません。それこそ無限の可能性があるのですから。もしかしたら、僕のように目がものすごく悪いということが、将来どこかの環境では有利なものとなるかもしれないのです。種を将来的にも確実に残し伝えていくためには、種の中にできるだけ多くの可能性を残しておくことが有効になってきます。現在ではイレギュラーと考えられるものだって、種の生存戦略から考えれば大事にした方がよいと言えるのです。
これは、文化にも言えます。よく例で取り上げられるのが、19世紀のアイルランドのジャガイモ飢饉です。19世紀のアイルランドはイギリスの支配下にありました。イギリス政府が農業に重税をかけたため、アイルランドの農民たちは農作物の選択集中を行い、収穫物を得やすいジャガイモの生産に集中しました。しかし、この効率化を狙った選択集中が仇となり、ジャガイモの疫病菌の流行による大飢饉でアイルランドの人口が4分の1ほど減少します。生き残った人たちもアメリカ合衆国などへ何百人も移住したため、アイルランド語話者や文化の担い手が減るなど大きな打撃を受けました。この時に移住したアイルランド移民の子孫に、あのケネディ大統領がいます。
選択集中や効率化というのは、短期的な経済の視点ではよいですが、危険性もあるのです。『鬼滅の刃』で鬼が人間に勝てなかったのは、多様性をもつ人間に対して、たった一人の鬼の血に頼っていた多様性の欠如が理由だったのかもしれません。そんな訳ないかな。読んでいない人には意味不明ですみません!
世界遺産というのは、まさに世界の多様性を代表するものです。世界には僕たちが普通に暮らしていると出会うことのない、さまざまな文化や自然があります。それをしっかり守って伝えてゆく。古臭くて不便な伝統的集落や開発の邪魔になる自然環境なども、世界遺産として守っていくべき理由はそこにあると思います。
今年は世界遺産委員会がありませんでしたが、来年の世界遺産委員会でどんな未知の文化や自然と出会えるか楽しみですね。
今年もあと残りわずかとなりましたが、お体には気をつけて、よい年をお迎えください。今年もありがとうございました。
(2020.12.10)