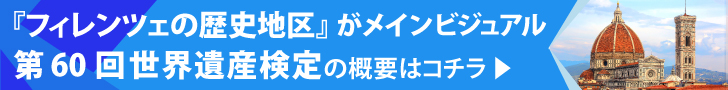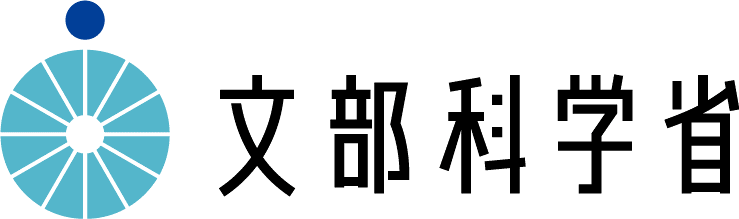古都フィレンツェにある謎の小窓の正体は?
第60回検定の申し込みがはじまりました。今回のメインビジュアルで取り上げたのは、『フィレンツェの歴史地区』です。ルネサンスの文化や建築を今に伝える街で、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ボッティチェリなど多くの芸術家が活躍しました。

フィレンツェには数多くの有名な見どころがあります。ブルネッレスキが設計した巨大なドーム天井をもつサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂はじめ、街の中心地に立つミケランジェロのダヴィデ像やフィレンツェを支配したメディチ家の美術品を集めたウツィフィ美術館、宝石店が軒を連ねるヴェッキオ橋など枚挙にいとまがありません。

そんなフィレンツェで店先にある“小さな窓”が注目を集めているのはご存じでしょうか?店の外壁に開けられた窓は縦30センチ、横20センチほどの窓です。これは「ワインの小窓」(Buchette del vino)といいます。もともとはその名の通り、ワインを受け渡す用途でつくられました。500年ほどの歴史のある窓で、一時は使われていないものも多かったといいます。しかし新型コロナ・ウイルスの流行以降は、ソーシャル・ディスタンスを保って商品の受け渡しをできると注目が集まり、現在は観光資源としても活用されています。

ペストから市民を守った「ワインの小窓」
メディチ家のフィレンツェ支配を確立したコジモ・ディ・メディチは、地主に対して、所有するブドウ畑の収穫からつくったワインの余りを、街の邸宅で少量ずつ、直接販売することを許しました。地主が販売を許されていたのは自家製造のワインのみで、1回あたり1.4リットルまででした。この直売によって中間業者が排除され、庶民は店頭よりも安価にワインを買えるようになったといいます。

1630年代にフィレンツェではペストが猛威をふるった時代に、「ワインの小窓」は病気の防波堤となりました。もともとは購入者が持参した瓶を受け取り、そこにワインを入れて販売するという方法をとっていましたが、ペストが流行すると瓶に触って病気に感染することがないように、窓にワインを注ぐための注ぎ口を設置し、購入者はそこからワインを受け取ったといいます。
ルネサンス時代のフィレンツェは、水の汚染がひどく、飲むと病気にかかる可能性が高かったため、ワインは必需品でした。そのためどんなにペストがまん延してもワイン売買はやめるわけにいかず、「ワインの小窓」はとても役立ちました。

「ワインの小窓」は1700年代にピークを迎えます。当時フィレンツェには数百もの「ワインの小窓」があったといいます。しかし、時がたつにつれ使われなくなり廃れていき、第二次世界大戦の際に壊されたものもありました。現在「ワインの小窓」はトスカーナ地方に170カ所以上残っているとされ、コロナ流行後はレストランやバー、ジェラート店などの10カ所以上で復活したといいます。
フィレンツェを訪れた際は「ワインの小窓」を探してみて、その歴史に思いをはせながら、グラスをかたむけるのも良いかもしれません。

フィレンツェの歴史地区
登録基準:(i)(ii)(iii)(iv)(vi)
登録年:1982年登録/2015年、2021年、2023年範囲変更
登録区分:文化遺産